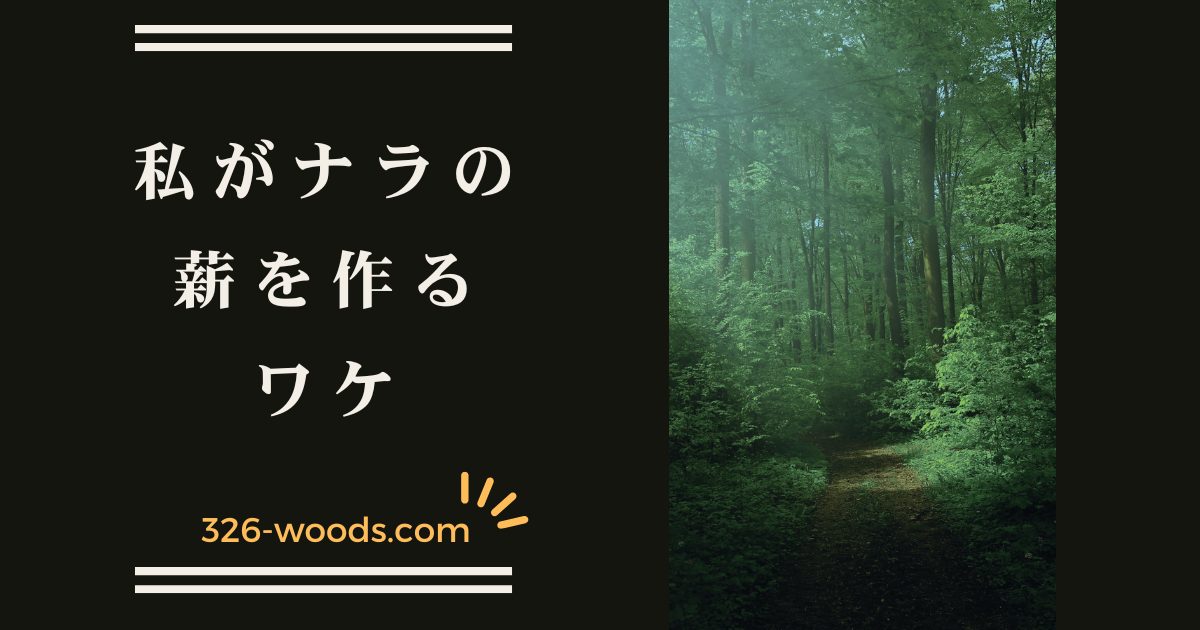私が原木にこだわるワケ
当社は薪の原料となるナラの原木に一番にこだわっています。
取り扱う原木は寒い時期に切り出した材木だけを使っている。
薪屋さんでも年間を通じて販売している方は、切り出し時期にこだわらない方もいる。
ただそれが悪い訳ではない。

寒い時期というのは、木々が落葉して根から水分を吸わなくなった時期をいう。
秋10月下旬から1月頃までに伐採した木にこだわっている。
正直なところ、その時期は忙しく伐採量も限定されてしまう。
量よりも質にこだわる当社だからこそ、大切にしているポイントのひとつである。

実は冬の原木は水分量も少ないだけでなく、割って薪にした時の乾燥がとても早い。
夏の木は、水分が多く含まれていて柔らかく虫たち(カミキリ虫など)が好き好んで食べる。薪棚でよく見かける白い粉がふいたようになっているのは、虫たちが食べた証拠だ。
よって原木は、最終的な薪の仕上がりを決める重要な点になる。
薪の質とは?
薪の質と言われると、一番に「含水率」を思い浮かべる方も多いのではないか?
当社の薪は含水率10~15%で出荷しているが、当然のことで今更こだわる点ではない。

実は、薪の見た目もとても重要です。
ナラの木はとても堅い木なので、木の繊維がまっすくに伸びたものもあれば、途中に節があって独特の形も多い。
私は薪自体がひとつの芸術品に近いものと考えている。

結局、燃やせば灰になるんでしょ?と言われるが、個人的には薪が燃える姿まで楽しんでもらいたい。
薪の香り(嗅覚)・薪の燃える姿(視覚)・薪の爆ぜる音(聴覚)は人間の五感を刺激する。もしこれに薪ストーブ料理を加えるのであれば、食べる(味覚)と薪をくべる(触覚)も同時に楽しめるのではないだろうか。

今後、薪の辿り着くところ
近年、軽井沢周辺の薪市場は需要(購入したい方)と供給(生産する方)のバランスが崩れてきている。
コロナ渦から軽井沢バブルが始まり、別荘の建設ラッシュが今でも続ている。軽井沢の家=薪ストーブのイメージが強い。薪ストーブの燃料となる薪を生産する薪屋さんが一気に増えた。
またに市場調査として自分で他社の薪を購入することがある。
薪屋さんは、質より量のところもあればまたその逆もある。安いのには不安がある。本当にそれでいいのか?

正直なところ言いますが、薪屋さんは儲かりません。
機械化が進んでも山から切り出して最終的な薪に仕上げるまで、重機のガソリン代や人件費、運搬費など多くの費用が発生します。
単に燃やせればいい、自分の土地から適当な木を切って原材料にすればいい。
割り方や乾燥具合も気にしないのであれば話は別です。それは私は違うと思っています。

薪はある種の嗜好品として捉えられて、生活を豊かにする1つのツールであると考えます。
みなさんも、ちょっとした贅沢で薪にもこだわってみたらいかがでしょうか。
きっと今より薪ストーブをもっと楽しくなるはずですよ。