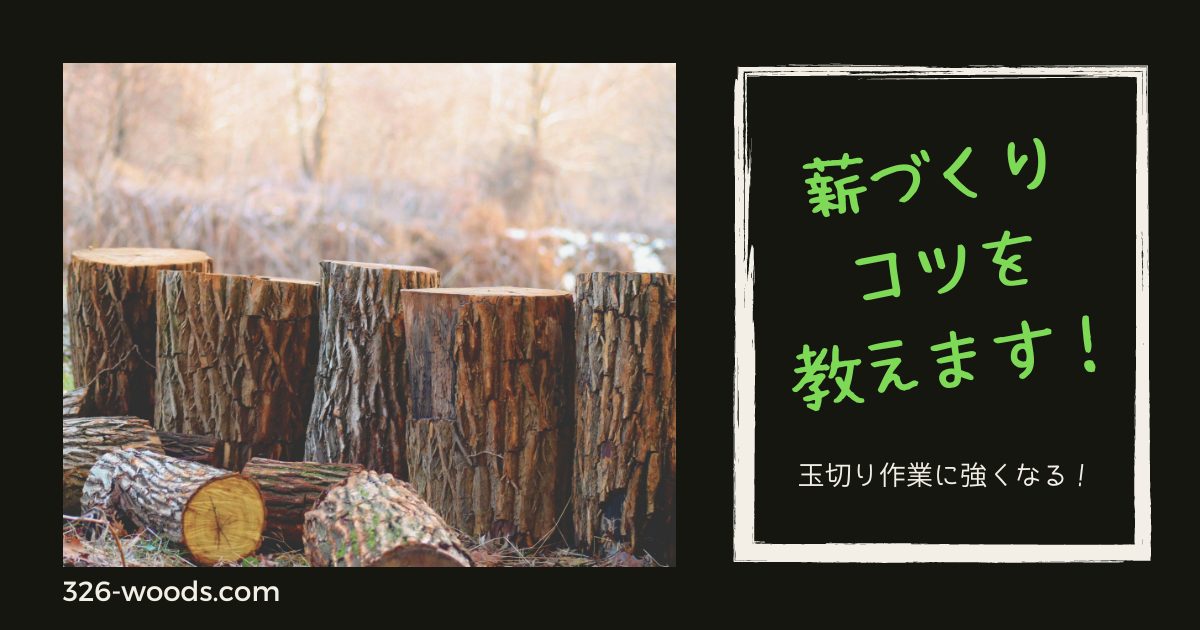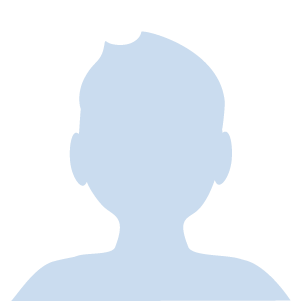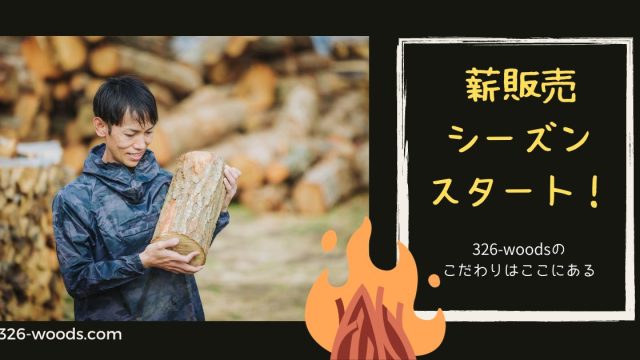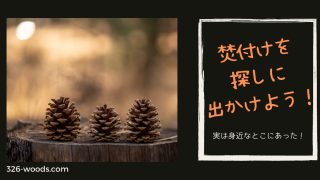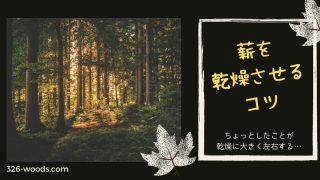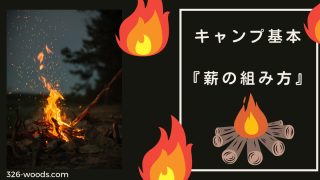お久しぶりの薪屋のごめさんです!
梅雨になって薪の乾燥具合が気になる時期になりました
長雨が続くとどうしても天日干しの薪にも湿気がこもってしまうので
とにかく早く梅雨明けを願っています!
乾燥場所が風通しの良いところなので乾燥はとても順調にすすんでいます!
今回は薪割りをする前作業の玉切り作業でちょっとしたコツをお教えします!
チェーンソー の目立てが一番!
そして恐らく多くの人は、
切れるチェーンソー=排気量が強いものというイメージかと思います。
私も昔はそうでした…グングン大きな音を立てて切っていくチェーンソーを見るとあたかもたくさん切っている錯覚に陥ります。
でも、実は違います!
チェーンソーの目立てが一番重要なんです!
排気量の小さいものでもしっかりと目立てをしていれば、太くて硬い木も楽々玉切りできます
逆に言えば、目立てができていないチェーンソーをいくら使っても、燃料だけ使うだけで太い木を切るのにもとても時間がかかってしまいます。
チェーンソーは、使ったら必ずメンテナンスと目立ては絶対してくださいね!
ネットでたくさん目立て道具が売っていますが、基本は角度を30度で目立てができるように何度も練習してみてください。分からない場合は、近くの農機具取り扱い店で聞いてみるのもいいかもしれないです!
私が使っている自動目立て機はこちらです↓↓↓
ごめさん直伝…玉切りの極意…
平らな場所で作業をするべし!
玉切りの基本中の基本として、原木を必ず平らな場所へ持っていくこと!
平らな場所ではチェーンソーの刃を入れた時にどちらに力(応力)が加わっているか
分かりやすいからです。玉切りする場所は、砂利やアスファルトではない方が良いです。
それはチェーンソーの刃が砂利やアスファルトに少し触れた瞬間にチェーンソーが切れなくなってしまいます。(この場合、目立てをしないと作業効率が極端に落ちます)

安全面として、玉切りした木が思わぬ足元に転がってきてケガをする時があります
正直、打撲だけではすまない…骨折する時もあります。
平らな場所を探すことは意外と難しいので、木が水平になるように切り込みを入れた枕木などにどっしりと置くのも一つの方法かもしれません。
ギリギリのところまで切って回すべし!
玉切りをしているとチェーンソーの刃を、どのくらいまで木に入れたほうがいいのかよく聞かれます。実は、チェーンソーの刃は地面ギリギリまで切ってください。
↓写真ではチェーンソーの刃をギリギリまでいれた原木↓

ギリギリまで切った原木が体で動くようであれば、足で蹴って原木を180度回転させる。
もし重すぎて回転できない場合は、
無理をしないでフェリングレバーを使ってください。

フェリングレバーの使い方は、フックを木に引っ掛けてからレバーを押し下げれば
原木が手前に転がるようになります。
バーが挟まれることを恐れない!
回転させた原木には玉切りの刃筋ができていて、そこにチェーンソーの刃を入れて
上に持ち上げるだけで玉切りがどんどんできてしまいます。

以前はガイドバーが挟まれることも多く、その度に力技で抜いていた記憶があります
常に木の重心がどこにあるのか意識することが大切です!
チェーンソーの切り上げはキックバックが起こりやすい動作ですので、必ず保護具などを身に着けて作業を行いましょう!

きっとコツをつかめ玉切りが10分で原木3~4本(2m)処理できちゃったりします
毎日コツコツと玉切りすればあっという間に薪ができちゃいます。
まとめ
玉切り作業はどうしても危険(大けが)の可能性が高い作業です
下手にビビる必要はありませんが、
- 基本動作を守ること。
- 道具のメンテナンスを欠かさないこと。
- 無理はしないこと。(適度な休憩と水分補給)
これだけでも未然に危険を回避できると思っています!
皆さんも楽しく薪づくり(薪活)を楽しみましょうね!
ごめさんの最新情報はTwitterやインスタでも毎日の作業を公開中です。
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓